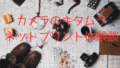夏の夜空を彩る筑後川花火大会。その華やかな光景の背後には、実は久留米藩主・有馬家と水天宮の深い歴史が隠されています。
平家の悲劇に由来する水天宮が久留米の地に根づき、やがて江戸に渡って「情け有馬の水天宮」と呼ばれるまでの物語。そして、疫病退散を祈って始まった花火が、今では西日本最大級の夏の祭典へと発展しました。
今回は、有馬家と水天宮、そして筑後川花火大会をめぐる歴史を探訪してみましょう。
水天宮のはじまりと平家伝説
水天宮の総本宮は福岡県久留米市に鎮座する「水天宮」です。
その由来は、壇ノ浦の戦いで入水した安徳天皇や建礼門院、二位の尼を祀ったことにあります。平家の悲劇を慰めると同時に、水難除けや安産の神として広く信仰を集めてきました。
ここで大切な役割を果たしたのが久留米藩主・有馬家です。代々の藩主は水天宮を庇護し、社殿の造営や祭礼を支えました。
江戸に渡った「有馬家の水天宮」
1818年(文政元年)、9代藩主・有馬頼徳は水天宮の分霊を江戸の上屋敷に勧請しました。
これが「江戸水天宮」、現在の東京・日本橋水天宮の起源です。
当初は藩邸内の社で、参拝は限られていました。しかし庶民の信仰があまりにも篤かったため、毎月5日にだけ参拝が許され、「情け有馬の水天宮」として江戸っ子たちに親しまれるようになりました。
明治の変革と東京水天宮の発展
明治維新によって有馬家の屋敷が失われると、水天宮は青山を経て、1872年に日本橋蛎殻町へと遷座します。以来、安産祈願の神社として多くの人に信仰され、現在の社殿は2016年に新築された近代的な建物となりました。
興味深いのは、今も宮司は有馬家の子孫が務めており、数百年にわたる有馬家と水天宮の関係が脈々と受け継がれていることです。
筑後川花火大会と水天宮
ここで忘れてはならないのが「筑後川花火大会」です。
実はこの花火大会の起源は、1650年(慶安3年)に久留米藩主・有馬忠頼が水天宮の夏祭で悪疫退散と水難鎮護を祈願して花火を打ち上げたことにあります。
その後、江戸中期には「水天宮奉納花火」として定着し、藩士や町人が一体となって盛り上げる行事になりました。
現在では毎年8月5日に開催される西日本最大級の花火大会へと発展し、川面を彩る大輪の花火は久留米の夏の風物詩となっています。
つまり筑後川花火大会は、単なる夏の娯楽ではなく、 有馬家と水天宮の信仰の歴史を現代に伝える祭礼なのです。
まとめ
今回は、久留米にあります水天宮の歴史を紹介しました。
- 久留米の藩主・有馬家が守った水天宮
- 江戸に渡り、庶民信仰を集めた「情け有馬の水天宮」
- 明治以降も宮司は有馬家が務め、信仰を継承
- 筑後川花火大会は水天宮の祭礼から始まった伝統行事
水天宮の歴史をたどると、有馬家の祈りと庶民の信仰、そして華やかな花火大会までが一本の線でつながっていることに気づきます。
江戸と久留米を行き来しながら、神と人、そして文化をつないできた「有馬家と水天宮」の物語は、今も私たちの生活の中で生き続けているのです。