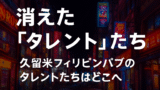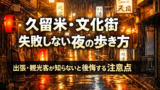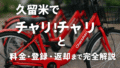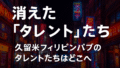福岡県久留米市にある「文化街」。
今ではネオンが灯り、スナックやバー、居酒屋が軒を連ねる“夜の街”として知られています。
しかしその始まりは、意外にも戦後の復興とともに生まれた「人々の憩いの場」だったのです。
■ 戦後復興とともに生まれた「文化街」の原型
文化街のルーツをたどると、戦後すぐの昭和20年代初頭に遡ります。
当時の久留米は空襲の被害を受け、市街地の再建が急ピッチで進められていました。焼け野原になったエリアには「新興市場」と呼ばれる屋台村や仮設の商店が立ち並び、市民の生活を支える場として賑わっていたのです。

その後、日吉町一帯に「文化会堂」という映画館が誕生。映画や演劇、食事など“文化の香り”が漂う新しい娯楽地として注目を集め、この周辺がいつしか「文化街」と呼ばれるようになっていきました。
■ 飲み屋が増え始めたのは昭和30年代
飲み屋街としての文化街が形づくられたのは、昭和30年代(1950〜60年代)のこと。
この頃、日本は高度経済成長期に突入。久留米でもブリヂストンをはじめとしたゴム産業が発展し、人々の暮らしにゆとりが生まれました。
会社帰りに一杯、休日に仲間と集う…。そんな“夜の社交場”として、居酒屋やバー、クラブが少しずつ姿を現します。
市内には屋台文化も根付いており、焼き鳥の香ばしい匂いが夜風に漂う、そんな光景がこの頃の久留米の風物詩でした。
■ 昭和40年代後半、「文化街」へ集約が進む
当時、久留米の歓楽街といえば「新世界」地区(六ツ門町)が中心でした。
ところが昭和40年代に入ると、飲食・風俗関係の店舗が次第に新興エリア・文化街へ移転し始めます。新しい道路整備や店舗区画の拡大が進んだことで、文化街はよりアクセスの良い“新しい夜の街”として台頭。
昭和40年代後半には、久留米で最も華やかな歓楽街としてその名を轟かせます。まさにこの時期、久留米の夜は一気に輝きを増したのです。
■ 現在の文化街とこれから
現在の文化街には、老舗のスナックから若者向けのバーまで、約500軒以上の飲食店が並ぶといわれます。
昔ながらの情緒を残しつつも、新しいスタイルの店も増え、「久留米の夜を象徴する街」として今も進化を続けています。
戦後の焼け跡から立ち上がり、人と人が再び集い、笑い、語り合う場所として生まれた文化街。その灯は、令和の今も変わらず久留米の夜を照らし続けています。
まとめ
今回は、文化街の成り立ちを紹介しました。
- 文化街の起源:戦後(昭和20年代)、日吉町周辺の映画館「文化会堂」から
- 飲み屋が増えた時期:昭和30年代(高度成長期)
- 本格的に歓楽街化した時期:昭和40年代後半
- 現在:老舗スナックと若者バーが共存する久留米の夜の中心地
最近はお客の数よりキャッチの数の方が多いと揶揄されることもある文化街ですが、文化という名に恥じぬような昔ながらの風情ある飲み屋街に戻ってほしいものですね。