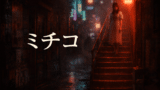ネオンは湿っていた。
雨は降っていないのに、路地の空気だけが濡れている。
男は真依を探していた。
店の名前は覚えている。
階段も覚えている。
ドアの重さも、笑い声も。
だが、確信だけがない。
扉を押すと、小さな鈴が鳴った。
「いらっしゃい」
カウンターの奥で、年配の女がグラスを拭いている。
知らない顔だ。
ガールズバーというより、寂れた場末のスナックという雰囲気だった。
男は少しだけ店内を見回す。
奥の席。
壁のポスター。
あの夜、真依が立っていたはずの場所。
「おひとり?」
「ああ……」
男はカウンターに腰を下ろす。
氷の音がする。
テレビは消えている。
他に客はいない。
「何にします?」
「ハイボールを」
グラスが置かれる。
琥珀色が揺れる。
男は、何でもない声を装って言う。
「ここ、前に来たことがあって」
「そう」
女は顔を上げない。
「真依って子、いるよな?」
拭いていた手が、一瞬止まる。
「……誰のこと?」
「細い子で、おでこが広くて、笑うと少しだけ目が細くなる」
沈黙。
氷が、ゆっくり溶ける。
女はゆっくり男を見る。
「うちには、そんな子いないよ」
「前はいた」
「いつの話?」
男は答えに詰まる。
先月だったか。
もっと前だったか。
時間の感覚が曖昧だ。
「源氏名かもしれない。本名は知らない」
女は小さく息をつく。
「文化街はね、源氏名だらけだよ」
男は笑わない。
「でも、いたんだ」
その声だけが、やけに真っ直ぐだった。
女はカウンター越しに男をじっと見つめる。
「……あんた、どこでその名前聞いたの?」
「ここだよ」
「違う」
女の声が少し低くなる。
「その名前を出す人は、たまにいる」
「どういう意味だ?」
「決まって、あんたみたいに探してる顔してるよ」
店の空気が、少しだけ重くなる。
「昔、このあたりで亡くなった子がいた。本名は……ミチコって言った」
男は何も言わない。
男の指が、グラスを強く握る。
「文化街のミチコ。噂だからね。信じるかはあんた次第」
男の心臓が一度、大きく鳴る。
女は、続けて言う。
「選ばれた男の前にだけ現れるって話、聞いたことない? 心を落とした男にだけ、ね」
それから女は、ゆっくり、ミチコにまつわる伝説を語りはじめた。
つづく