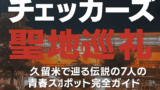石橋凌(いしばし・りょう) は、福岡県久留米市出身の俳優・ミュージシャンである。
ロックバンド ARB(Alexander’s Ragtime Band) のボーカリストとして日本のロック史に名を刻み、俳優としては日本映画の暴力性や孤独、社会の影を体現し続けてきた存在だ。
華やかなスターというより、常に「時代の裏側」に立ち続けてきた表現者。音楽界でも映画界でも独特な存在感を放っている。
その原点には、地方都市・久留米が抱えてきた独特の空気がある。
石橋凌のプロフィール・略歴
- 名前:石橋 凌(いしばし りょう)
- 生年月日:1956年7月20日
- 出身地:福岡県久留米市
- 職業:俳優・ミュージシャン
- 代表分野:ロック(ARB)、映画・ドラマ
- 家族:妻・原田美枝子、娘・優河/石橋静河
久留米で生まれ育った石橋凌は、1970年代後半に音楽活動を本格化させ、やがて日本ロック界の異端として注目を集める。
ARB結成|日本語ロックに刻まれた怒り
1977年、石橋凌はロックバンド ARB を結成。
1978年、シングル 「野良犬」 でメジャーデビューを果たす。
ARBの音楽は、当時主流だった歌謡ロックとは一線を画していた。
- 社会への違和感
- 管理社会への反発
- 行き場のない若者の怒り
それらを、直接的な言葉と荒削りなサウンドで叩きつけた。
石橋凌のボーカルは「歌う」というより、感情をそのまま吐き出す行為に近い。
この姿勢は、のちの俳優活動にも一貫して流れていく。
ARB代表曲ベスト5(解説付き)
個人的に一番好きな歌は、『After ’45』だ。戦争が終わった1945年の前と後、この大きな違いを静かに力強く歌い上げている日本音楽界に残る名曲。
1.野良犬
ARBの原点であり、石橋凌という表現者の核。
社会に飼いならされない存在を描いたこの曲は、今も色褪せない。
2.魂こがして
「生きること」そのものを燃焼させるような名曲。
石橋凌の演技に通じる切迫感がすでにここにある。
3.After ’45
戦後日本への疑問を突きつけた社会派ロック。ARBが思想的バンドであったことを示す代表作。松田優作初監督作品『ア・ホーマンス』主題歌。
4.さらば相棒
荒々しさの裏にある、不器用な情を描いた一曲。
俳優・石橋凌の“静”の側面と響き合う。
5.Long, Long Way
ARB後期の楽曲。若さだけでは進めなくなった時代の迷いと成熟。
俳優・石橋凌の誕生|映画界への転身
1986年、映画 『ア・ホーマンス』 で本格的に俳優デビュー。この作品で高い評価を受け、キネマ旬報新人賞を受賞する。

以降、石橋凌は
- 北野武
- 三池崇史
- 園子温
- 清水崇
といった“危険な監督”たちに重用される。
主な出演作
- 『キッズ・リターン』

暴力性、狂気、沈黙。
石橋凌は「説明できない男」を演じることで、独自の地位を築いた。
松田優作との関係|同時代を生きた別の獣
石橋凌を映画俳優の道に誘ったのは、松田優作だった。松田優作は、初監督作品映画『ア・ホーマンス』に石橋凌を誘った。その時の石橋凌は、ミュージシャンとして生きていきたいと思っていた為、俳優への道となる映画出演を迷っていた。そんな石橋凌に松田優作は「映画で顔を売ってからミュージシャンも続けたらいいじゃないか」と言い、この言葉で石橋凌は映画初出演を快諾したとのことだ。
2人はともに、同じ時代の日本社会に違和感を抱き続けた存在だった。松田優作が都市のアウトローを象徴するなら、石橋凌は地方(久留米)から来た現実の反骨だった。様式美の松田優作、生身の危うさの石橋凌。2人の存在が、日本映画をより立体的にしたのは間違いない。
海外進出と現在の活動
2000年代には、ハリウッド映画 『THE JUON/呪怨』 に出演。
SAG-AFTRA(米俳優組合) にも所属し、国際的に活動の幅を広げる。
近年は
- Netflix『全裸監督』
- 映画・舞台・音楽活動
などを通じ、年齢を重ねたからこその存在感を見せている。
石橋凌・久留米聖地巡礼|街の空気を歩く
石橋凌の久留米聖地巡礼に、「公式スポット」はほとんど存在しない。強いてあげるなら、出身校である福岡県立久留米高等学校だろう。→MAPはこちら
巡礼ポイント(空気編)
- 筑後川河川敷
- 六ツ門・日吉町周辺
- 西鉄久留米駅周辺
- 名もなき路地や住宅街
ここにあるのは記念碑ではなく、息苦しさと広さが同居する地方都市の感覚だ。
ARBのロックも、映画での沈黙も、この久留米の街の空気から生まれたのだ。
まとめ|久留米が生んだ反骨の表現者
- 石橋凌は 福岡県久留米市出身
- ARBで日本語ロックの核心を担った
- 俳優として日本映画の暗部を体現
- 現在も第一線で活動中
石橋凌は、久留米が誇るスターというより、久留米が生んでしまった表現者だ。
そしてその存在は、今も静かに、しかし確実に響き続けている。