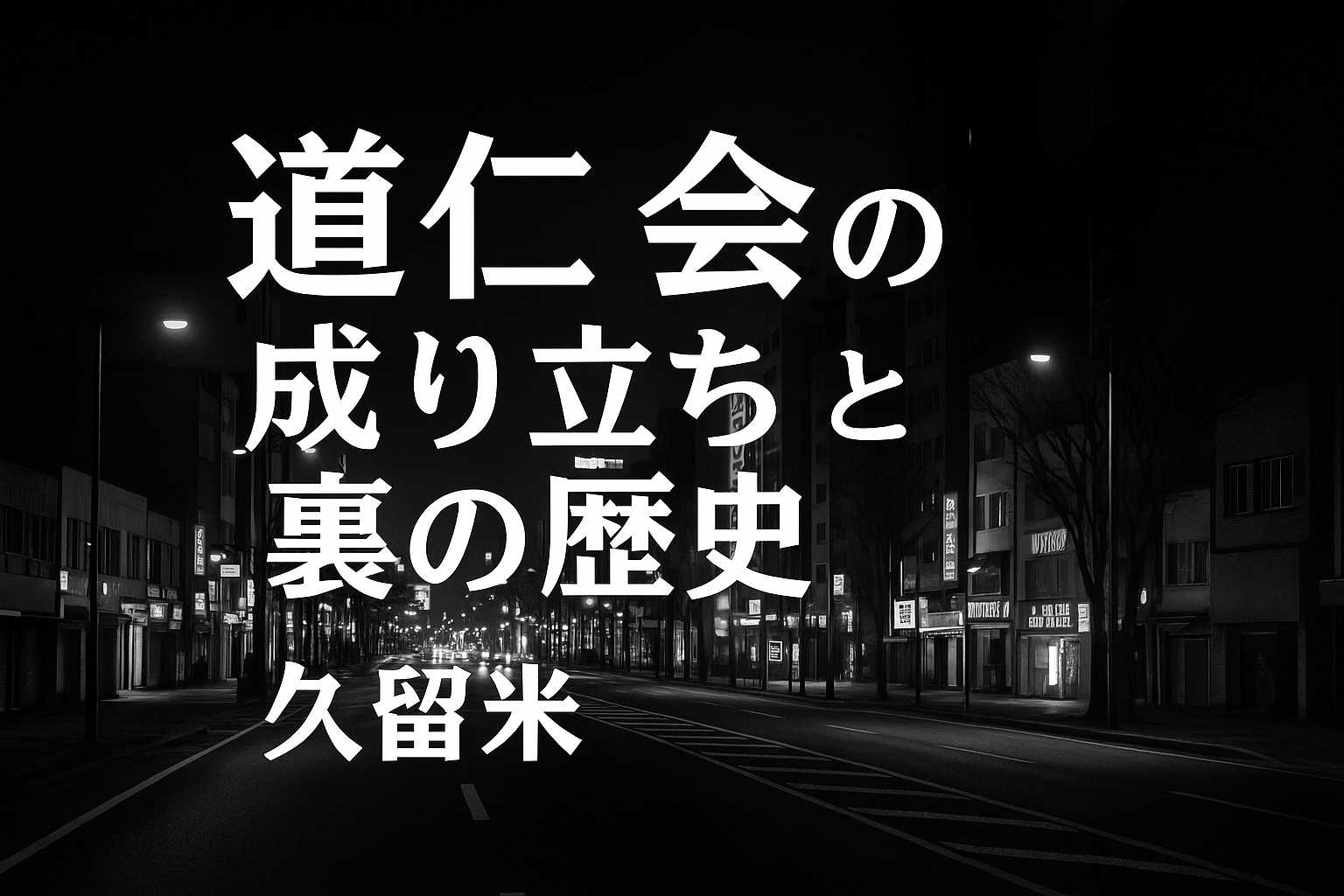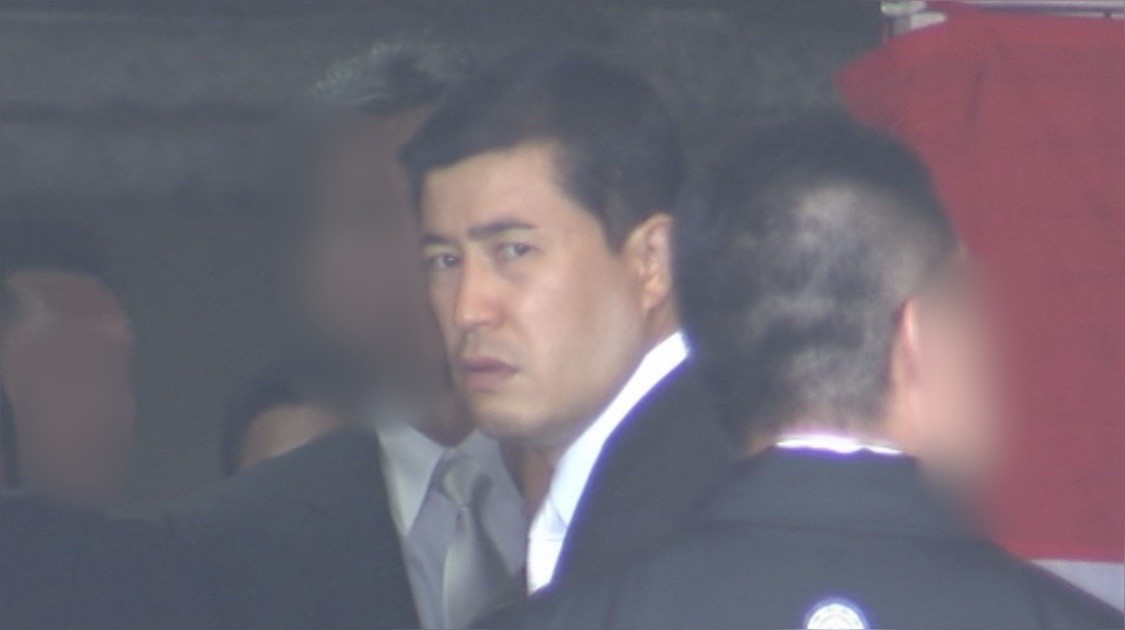久留米という町には、明るい観光地の表舞台だけでなく、戦後の混乱期を生き抜いた“裏の歴史”もある。
その中心にあったのが、久留米に本部を置く指定暴力団「道仁会」だ。数々の抗争を経て、やがて日本全域に名を轟かせる存在となった。しかし、その道のりは決して平穏ではない。外部勢力・山口組との緊張関係、そして内部から誕生した九州誠道会との激しい抗争——。
道仁会の歴史は、久留米という地方都市の戦後史そのものを映し出していると言っても過言ではない。
この記事では、久留米を舞台に育った道仁会の成り立ちから、山口組・九州誠道会(現・浪川会)との関係、そして現代に至るまでの歩みを、地域の歴史としてたどっていく。
観光や文化だけでは見えてこない、“もう一つの久留米史”を紐解いてみたい。
道仁会とは
道仁会(どうじんかい)は、福岡県久留米市に本部を置く指定暴力団。1971年、福岡県久留米市で複数の団体が合流して結成された。創設者は古賀磯次。九州南部の暴力団勢力の中で早い段階から組織化を進め、久留米市に本部を置いた。筑後地方を中心に、北九州・佐賀・熊本へと勢力を拡大した。
道仁会の特徴は、「地元主義」「家族主義」を掲げた運営方針であり、外部勢力への警戒心が強かった点にある。
山口組との関係と抗争
1970年代〜80年代にかけて、全国最大組織・山口組が九州進出を強化する中、道仁会は独立路線を貫いた。
これにより、道仁会 vs 山口組系組織の間で緊張が高まり、俗に山道抗争と呼ばれる断続的な抗争事件が発生した。
2000年代に入ると、山口組は九州進出を一時的に抑制し、代わりに地元系組織間の主導権争いが中心となる。
九州誠道会との分裂と抗争
2006年、道仁会の内部対立が表面化し、大牟田市を本拠地とする村上一家を中心とした勢力が離脱して「九州誠道会」を結成。
これが九州ヤクザ史上最大規模の分裂抗争を引き起こした。
抗争の経緯(年表)
| 年 | 出来事 | 概要 |
|---|---|---|
| 2006年 | 分裂 | 道仁会から九州誠道会が離脱、敵対関係へ |
| 2007年8月 | 大中義久三代目会長銃撃死 | 福岡市中央区で射殺される |
| 2007年11月 | 武雄市・一般男性誤射事件 | 市民が巻き添えで死亡、社会的衝撃拡大 |
| 2008〜2011年 | 抗争拡大期 | 久留米・大牟田・佐賀・熊本で連続発砲事件 |
| 2012年 | 抗争終息傾向 | 1年以上発砲事件なし、警察が“終戦”兆候と判断 |
| 2013年6月 | 九州誠道会が解散届提出 | 公式に抗争終結宣言 |
| 2014年6月 | 特定抗争指定解除 | 福岡県公安委員会が両組織の指定を解除 |
抗争の激化期には、民間人を巻き込む危険な状況も発生。
2007年(平成19年)11月8日に佐賀県武雄市で、整形外科病院に入院中の男性が暴力団組員に射殺された事件。一般市民が暴力団抗争に巻き込まれ、人違いで殺害された。武雄入院患者射殺事件、武雄事件とも呼ばれる。ー引用元:wikipedia「佐賀入院患者射殺事件」
2013年、九州誠道会の事実上の解散により、表向きの抗争は終息。しかし、警察関係者の多くは「静かな再編」と見る。
組織の再構築が進む中で、道仁会は再び一本化。2025年6月、代表者が四代目・小林哲治から五代目・福田憲一に交代した。
構成員は約310人。福岡県内の指定暴力団では最大規模を維持している。
抗争という「銃の時代」が終わり、今度は「経済を介した支配」へと舵を切る。
道仁会の現在と地域社会との関係
2020年代に入ってからの道仁会は、かつてのような派手な抗争を避け、「経済ヤクザ化」・「表社会への接触減少」が進んでいるとされる。
一方で、久留米・筑後エリアでは今なお建設業や不動産業界への影響力が指摘されており、地域経済との複雑な関係は続いている。
警察庁の指定暴力団一覧でも「九州最大級の地元組織」として位置づけられ、久留米を拠点とするその存在感は現在も無視できない。
地方都市における“裏の経済循環”
九州の地方都市において、暴力団と建設業界の関係は長年指摘されてきた。
公共工事、下請け取引、資材供給――一見健全に見える経済活動の陰に、暴力団関係者が“保証人”“仲介人”として入り込む構造がある。
久留米市や筑後地区では、バブル崩壊以後の不況下で中小建設業者が資金難に陥り、暴力団が融資・仲介・用地買収の役割を担うケースが増えたとされる。
こうして「道仁会=地場経済の影のスポンサー」という関係が築かれていった。
建設業との接点 ― “ケツ持ち”の構図
警察資料によると、道仁会関係者は過去に「建設工事の下請け契約」を巡る恐喝・脅迫事件にも関与したとされる。
工事現場の安全確保、資材搬入の調整、さらには地元有力者との交渉――表向きは“調整役”だが、実態は威圧と支配である。
地域経済に与える影響
建設業だけではない。風俗業、飲食業、金融、土地取引――暴力団の資金源は、地方都市に根差した経済活動の中に存在している。
その結果、暴力団の影響下にある企業が公共工事や地元イベントに関与するリスクも高まる。
行政側も危機感を強めており、福岡県では「暴力団排除条例」に基づき、反社会的勢力との契約を禁止。
暴力団事務所の立地に対して住民訴訟が起きるケースも増加している。
福岡・筑後地区での実態
久留米市京町に本部を置く道仁会は、筑後・佐賀・熊本北部に広がる産業圏に強いネットワークを持つ。
建設業界では、元組員が経営する「関連会社」「協力会」が複数存在し、暴力団排除条例に抵触しない範囲で活動しているとも報じられる。
一方、地元自治体や警察は“暴排協議会”を通じ、企業・金融機関・自治体が連携する情報網を整備。
建設業者に対しては「契約先の反社チェック」や「下請け契約の透明化」を義務化する動きが進んでいる。
福岡県警は2019年11月27日、福岡県久留米市北野町陣屋の砂利販売業「猪口産業」の男性代表者が指定暴力団道仁会系組員と密接に交際していたとして、暴力団排除措置に関する協定に基づき、公共工事の下請から排除するよう県や福岡市、北九州市、国土交通省に通報した。久留米市長門石4丁目の土木業「古賀建設」についても、男性代表者が同会系組員だったとして、通報した。
第三部:抗争の終焉と新たな戦場
経済支配への転換
抗争が終息した現在、暴力団の活動は“銃から金へ”と変化した。典型的なニュースは、2025年10月に起こった道仁会系組長の拳銃自殺である。これまで暴力で生きてきた老齢のヤクザは、銃が必要なくなった世界で自分の命を絶つ手段として銃を使用した。
特に近年目立つのは、特殊詐欺・不動産投資・人材派遣業・廃棄物処理業などへの進出である。
建設業界と同様に、地方経済の「現金主義」と「人脈主義」を背景に、裏社会が再び経済圏を掌握しつつある。
組織の若年化と再編
暴力団の高齢化が進む一方で、若年層の“反社ビジネス”志向も強まっている。
暴力団排除条例による締め付けの中、若手構成員が“会社経営者”“人材仲介業者”として合法的な顔を持つケースが増加。
道仁会もその例外ではなく、近年は「表社会との融合」が最大の特徴といえる。
今後の展望と地域が直面する課題
1. 経済の中に潜む“静かな暴力”
暴力団は、もはや通りで銃を撃つ存在ではない。
契約書の裏に名前を刻み、企業の資金の流れに入り込み、地域経済を内部から蝕む。
「見えない支配」にどう対抗するか――それが地方都市の次の課題である。
2. 行政と市民の連携
福岡県では、警察・自治体・金融機関・市民団体が一体となり、「暴力団のいないまちづくり」運動を展開中。
福岡県警は、暴力団犯罪の通報者に最大100万円を支給している。
地域の小規模業者や個人事業主に対し、契約前の反社チェック体制を導入する企業も増えている。
今後は、情報共有と教育が鍵となる。
3. メディア・報道の役割
「沈黙」が暴力団にとって最大の味方である。
地域メディア・ジャーナリストが、地元社会の裏面に光を当て続けることが、暴力の連鎖を断ち切る唯一の方法だ。
まとめ|戦後から続く「九州ヤクザ史」の象徴
道仁会の歩みは、戦後の混乱期から現代まで続く九州社会の裏面史そのものである。
山口組との抗争、九州誠道会との分裂抗争、そして社会的包囲網の中での変化――。
その歴史は「暴力団対策法」「特定抗争指定」など日本社会全体の法整備の進化とも深く関わってきた。
抗争の時代が終わっても、道仁会は消えていない。形を変え、業種を変え、金の流れを変えながら――地域社会のすぐそばに存在している。
2025年1月には、道仁会傘下組長らが自営業者に対し「俺たちはケツもちしよるとぞ」と脅迫して金銭を要求し、逮捕された。
現在の道仁会は、かつての覇権的勢力から一転し、生き残りを模索する組織へと変化している。
九州の裏社会を知る上で、その歴史を正確に理解することは、地域社会の実態を読み解く上でも不可欠だ。